お盆にはお墓参りに行く、というのは常識であり、それが共通認識である、という感覚は少し古いのかもしれません。
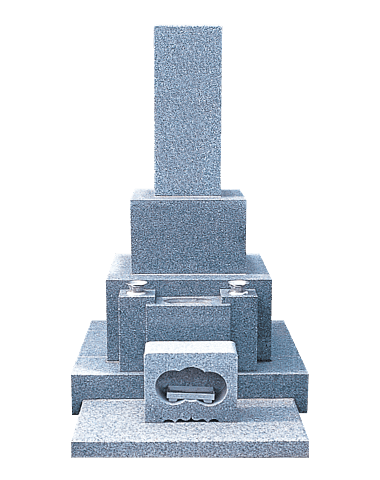
ある墓石会社が2015年に実施した調査によると、現代人の43%がお盆にお墓参りをしていないそうです。
その理由として最も多いのが「面倒くさいから」。
先祖と言っても、その亡くなった相手との関わりの深さ、愛着にもよりますよね。
実は自分もお墓参りには、ほぼ行っていません。理由は、面倒くさいから('Д')
家の敷地内にでもあればサクッと手も合わせられるんですけどね、墓が少し離れていると、貴重なお盆休みの時間を削るのがね~、っとなってしまいます。
わざわざお墓まで行かずとも、その先祖の遺骨をほんの少しだけでも持っておいて、その遺骨に対して手を合わせればいいのに、と、よく思います。
そんなお盆休みに、やってはいけない事の中に、海水浴があります。
理由は、死者に足を掴まれ、海に引きずり込まれるから('Д')

相当悪党の死者ですねこれは。
海でお亡くなりになられた方々の霊によるものなのかもしれませんが、供養に使われる塩にどっぷり浸かっているにも関わらず、それをされてしまったら、塩への信用はガタ落ちですね('Д')
海から上がってくることはないのでしょうか?なぜ海の中での勝負に執着するのでしょうか?こすいですね。

でも。上がってきたら海の家が黙ってないでしょうね。
そもそもお盆の始まりは、釈迦が弟子の木蓮の母親をこのあたりの日程で供養しちゃいなよ、と言ったことからだと言われていたり。

年一のそこのタイミングで一緒に便乗して供養してもらえなかったからといって、生きている者を海に引きずり込もうだなんて、そんなもの、供養してもらったところで成仏できようはずがありませんね。
お盆に海に入ってはいけない理由には諸説あり、その中には、お盆はクラゲが出始める頃だから入ってはいけないよ、というものもあるのだそう。
いっぺんにお盆が思いやりのあるピースフルな印象に早変わりですね。
ところで、お盆にお供えするお花には、バラは良くないのだそうです。理由は、トゲがあるので争いを連想させるから、だそうで、針も似た類なので、お盆に裁縫は良くないよ、って言われたりもするのだそう。
要するに、お盆は争いの無い、平和な優しい気持ちで、思いやりを持って過ごしましょうね、っていう素敵な期間なのかもしれませんね。
誰だ海に引きずり込まれるなんて言い出したのは('Д')!!
福正建設は今年、お盆休み9連休!!
海だ海だ(ΦωΦ)!!
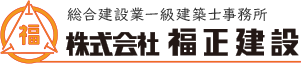




.jpg)













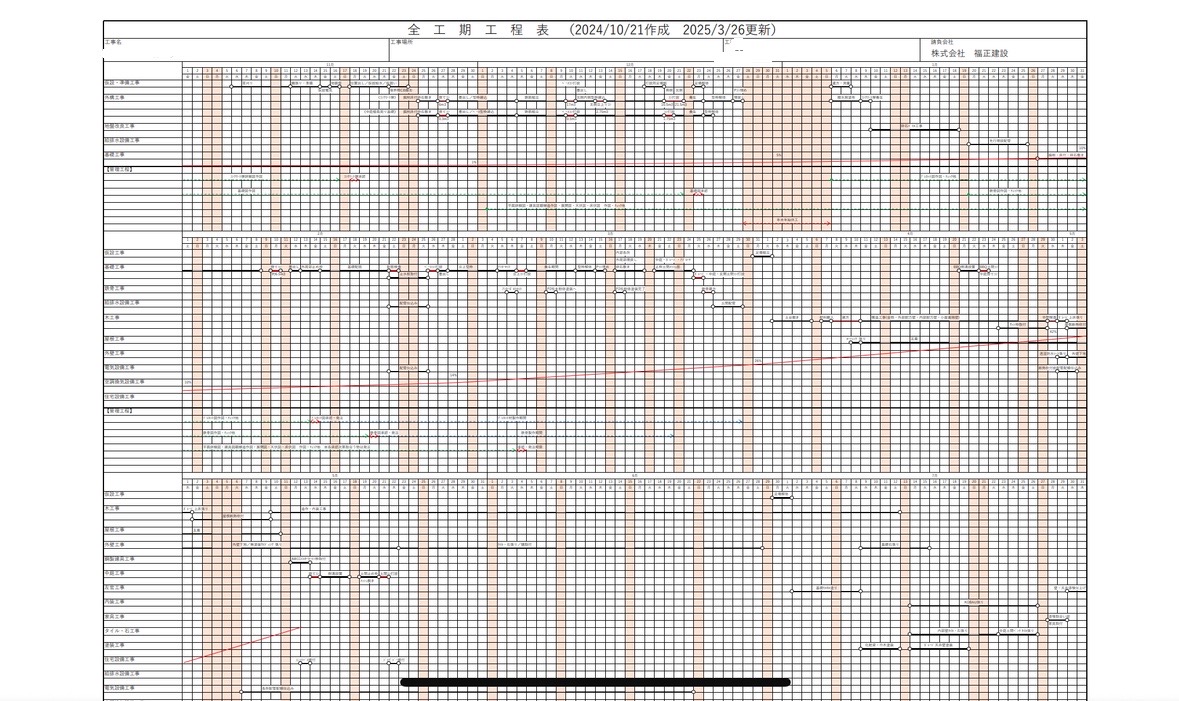
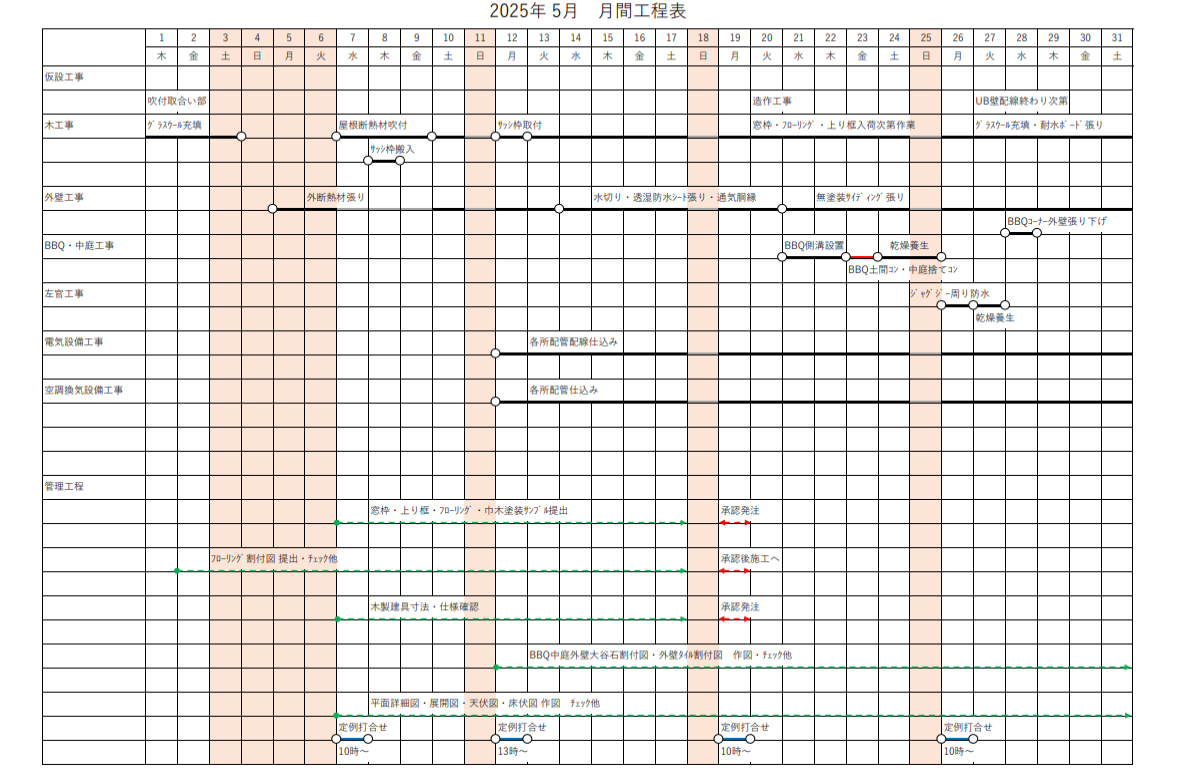



.jpg)

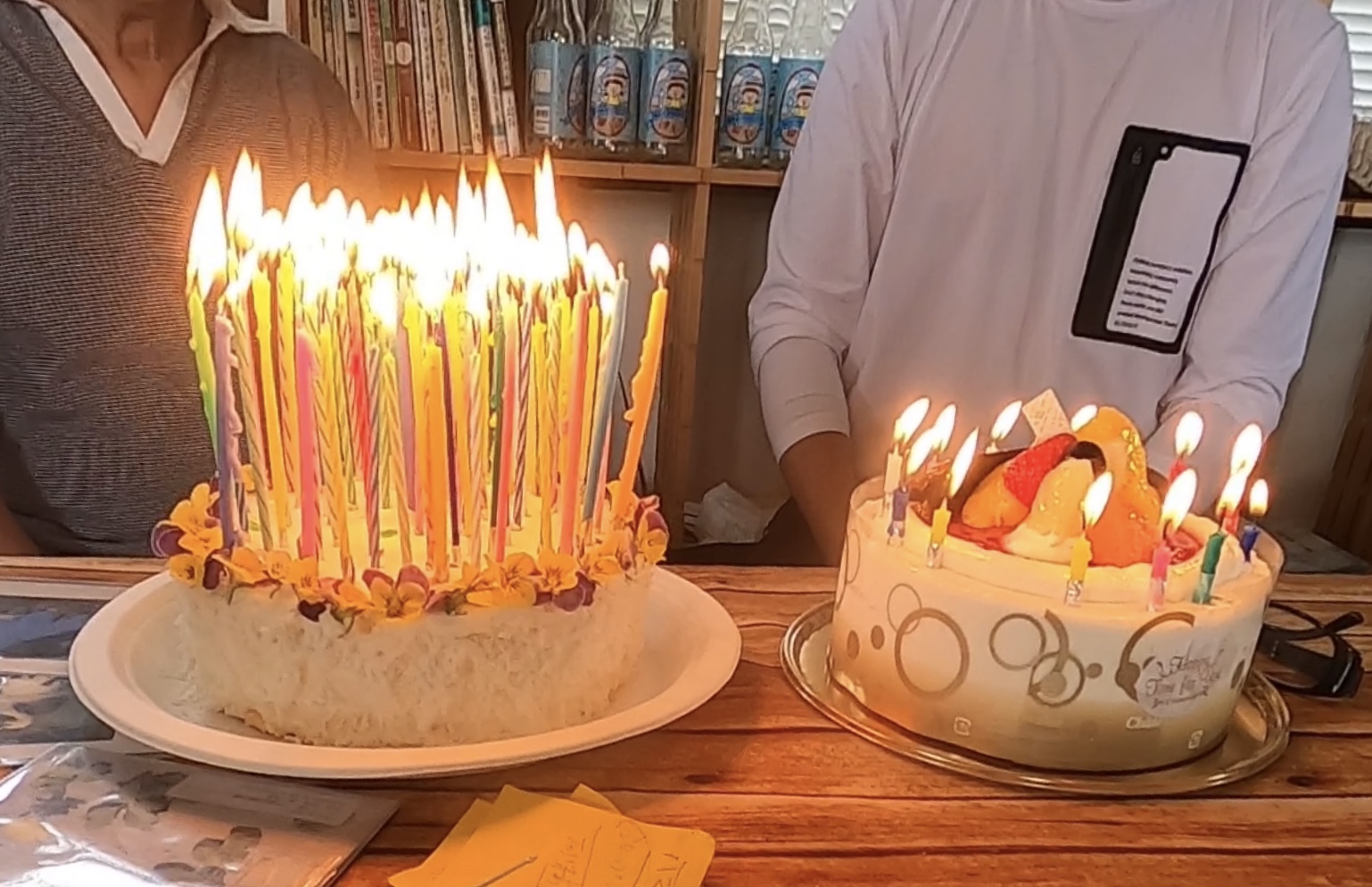

.jpg)
.jpg)
.jpg)





















