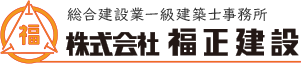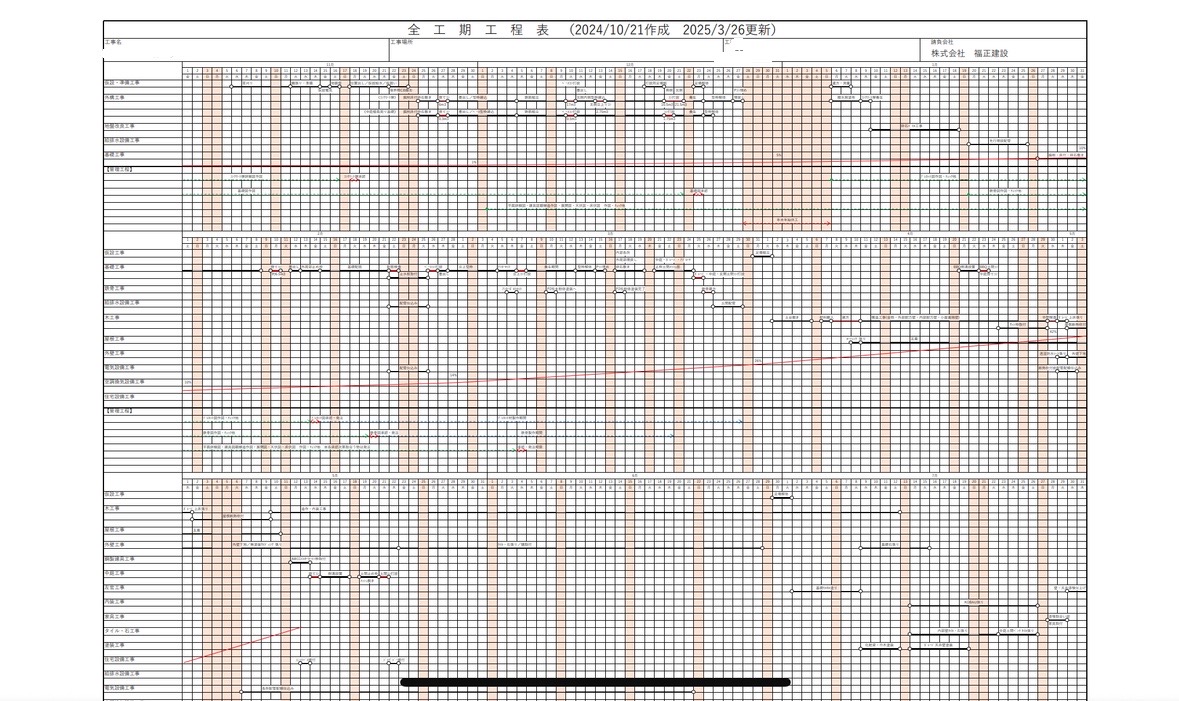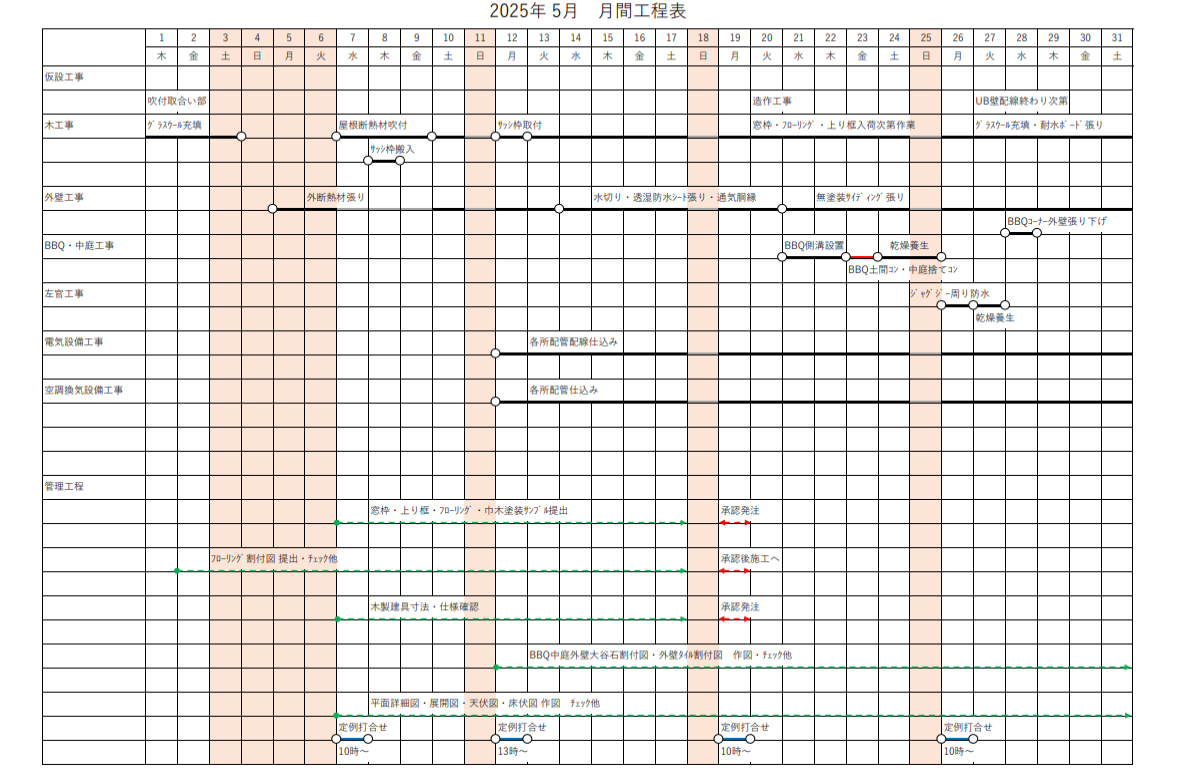板金で覆われた屋根。スレートという材質の屋根。瓦屋根など。
我々日本人には幼い頃から馴染みのある瓦屋根。どんなメリットや意味が隠されているのでしょうか。

まず第一に、瓦は長持ちします。そのため、メンテナンス費用も抑えられます。
ただ、それ以外の屋根材に比べ少し割高にはなるので、初期コストはかかります。それでも長い目で見るとお得です。
瓦は重たいです。地震などによって瓦の重みに耐えられず家が倒壊してしまった、というような話もたまに聞きますが、それは基本的には、強度に対する決まりが課される昭和56年以前の建物が多いんです。
瓦が重たかろうが、しっかりとそれに耐えられる造りにしてしまえば何の問題もありません。
台風などで瓦が飛んでくるから気を付けろ!というのも瓦を固定するようになる以前の建物が多いです。
昔は建物の強度も今より低く、骨組みに対し、瓦の重さは今よりもだいぶ負担になっていました。
そこで、あまりにひどい地震などが起きた際には、その揺れで瓦を剥がし、落下させ、自然と屋根を軽くし、倒壊を防ぐ。そのために瓦は固定しない、という工夫がされていました。
なので本当に古い家の瓦は、実際に強風などで飛ばされかねないのです。

いま時は瓦もデザイン性が豊富で、軽い物も沢山あります。もはや、瓦=和風、という時代では無いですね。

瓦に限らずですが、屋根の一番高い三角の頂点に君臨する部分、そこを棟(むね)と呼びます。
そして、瓦屋根において棟の高さを確保する部分を、のし瓦、と呼びます。

実は江戸時代などでは、この、のし瓦の高さで地位(身分?)の表現をする事ができていたのだそうです。
ここが高ければ高いほど、リッチであったり、格式高い、など。
見栄を張ってここを高くした人もいたかもしれません。
あいつあんなに高くしちゃって(笑) と、陰で笑われていた人もいたかもしれません。
或いは、何か基準が設けられており、誰でも好きな高さを選ぶことができたわけではなかったのかもしれません。

大工さんが、古いお屋敷の工事は大変だ、棟を跨ぐのに股が裂ける、と笑い話で言っていました。
古くから、3,5,7など、奇数は縁起が良いとされており、この、のし瓦も殆どが、奇数段になっているのだそうです。
知って見ると知らずに見るとでは、見える世界、感じる世界が全く違ってきます。
視点、価値観、考え方など、違って当たり前ですね。
世界をワクワクと、広く楽しく過ごせるだけの好奇心や知識を沢山手に入れることができると、今よりもっと心豊かになれるのかもしれません。
瓦からここに行きついたか、って感じですね(笑)